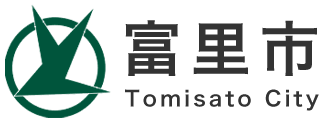武州ばやし
- [更新日:]
- ID:1178
市指定民俗文化財【無形民俗文化財】
武州ばやし(ぶしゅうばやし)

富里市十倉296-1(武州稲荷神社)
富里市役所前の道路を南に向かい、大堀のYの字交差点を右に直進すると、T字路にぶつかります。前方右側に見えるのが「お稲荷様」をまつる武州神社で、ここで武州ばやしが奉納されます。
武州地区は、明治の初めに埼玉県(武州)から移住してきた人々が、開墾したところです。
移住してきたころは原野であった高野牧の開墾に追われた厳しい生活でした。稲荷神社(武州神社)は、開墾作業の安全と農耕の安定を祈願して、移住してきた人々によって建立されたものです。また、開墾生活を共にする人々の精神的な結びつきと心のよりどころとしたものと考えられます。(武州ばやしはその一つの現われとして生れてきたのではないでしょうか。)
生活が安定した明治30年代ごろに、先祖に伝わる囃子(はやし)を始めました。始めのころは「武州ばやし」とは言わず、「武州の馬鹿面」と呼んでいたようです。娯楽のなかった開墾生活にあって、年一回のこの祭りは、苦労を共にする仲間との唯一の楽しみであったと思われます。
この囃子は昭和16年ごろまで続けられ、その後戦争や後継者不足などで中止されていましたが、昭和52年ごろに「武州ばやし」として復活しました。
お囃子というと、楽器の演奏だけのように思われるかもしれませんが、武州ばやしには踊り手もついています。この踊りには、神田五囃子の四丁目囃子に属する「外道のおどりと狐のおどり」と、仁羽の馬鹿囃子に属する「おかめおどり・ひょっとこおどり・恵比寿様の鯛釣り」があります。
現在「武州ばやし保存会」により伝統が受け継がれ、祭礼日である10月17日に、ユーモアたっぷりに奉納されています。
お問い合わせ
富里市役所教育部生涯学習課
電話: (中央公民館) 0476-92-1211 (社会教育班)0476-92-1211 (文化資源活用班) 0476-93-7641 (スポーツ振興班) 0476-92-1598 ファクス: (中央公民館/社会教育班/文化資源活用班) 0476-91-1020 (スポーツ振興班) 0476-93-9640
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます