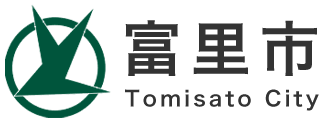地名に見る富里の歴史(第17回 総集編)
- [更新日:]
- ID:2468
平安
1155 久寿2
『下総国印東庄郷司村司交名』(郷村を支配していた者の名簿)に「中沢刈田弘益」と「新橋朝原清里」の記載があり、中沢、新橋の地名が記されている。
室町
1413 応永13
『香取造営料足納帳』によると、中沢は三谷兵庫殿の知行地(支配地)であった。(この中沢を鎌ヶ谷市の中沢とする説もある)
1591 天正19
大和の検地が行われる。検地帳『下総国印東庄大輪御縄打水帳』に「大輪(大和)」とある。
1594 文禄3
原家文書に、この年の中沢村の検地帳(表題なし)の写しがあり、その中に寺院分として、見正院、昌福寺、名正院、正(庄)蔵院、名正院、成(常)福院、長福寺、併福院、成正院がある。
江戸
1604 慶長9
久能の検地帳『下総国印東庄久能村御縄打水帳』に、久能は香取郡の印東庄である。との記載がある。
1628 寛永5
根木名石井家文書に、この年の根木名村の『田畑検地反別帳』が残っている。
1631 寛永8
この年7月に新田検知が行われ『佐倉領中沢村未新田新畑御縄打水帳』がある。
1642 寛永19
新橋観音堂に、新橋村の『年貢割付状』が残っている。
1664 寛文4
『寛文印知集』に佐倉藩主松平和泉守の領地として、日吉倉村、根木名村、高野村があり、また、高松村が松平和泉守と下総国高岡藩主井上筑後守の相給領地として記され、立沢村が井上筑後守の領地として記され、当時佐倉藩ではなかった特異な村のひとつである。
1700 元禄13
『下総国各村級(給)分』には、中沢村.大和村の石高と戸田能登守知行とあり、中沢には新中沢村の記載はなく、大和については元禄期あるいは直前に「大輪村」が大和村と書かれるようになった。
1722 享保7
享保の新田政策によって、日吉倉新田、久能新田、立沢新田が開発される。
1731 享保16
『下総国印旛郡高野新田検地帳』には、検地の字が、宮根と茂神台があり、今は宮根がない。
1734 享保19
原家文書の『中沢村丑年証文帳』には、中沢村と新中沢の農民が明確に区分されている。また高野の鈴木家文書の『検見ニ付被仰出請書』にも、中沢村と新中沢の名主、組頭、百姓代がそれぞれに連署捺印したものがあり、公的な諸帳簿には記載がないが、佐倉藩や村内では、明らかに新中沢が存在していた。
明治
1871 明治4
廃藩置県で富里市域は印旛県となる。
1872 明治5
「七栄村」「十倉村」が誕生する。
1873 明治6
千葉県誕生。
1884 明治17
「七栄村外十二カ村連合戸長役場制」の実施。(七栄村、日吉倉村、久能村、根木名村、大和村、新橋村、中沢村、新中沢村、立沢村、立沢新田村、高松村、十倉村、高野村の十三か村があった)
1889 明治22
富里村が誕生する。
昭和
1977 昭和52
日吉倉地区の西側に宅地造成された区域を大字名日吉台とする。
1985 昭和60
富里町誕生。
平成
2002 平成14
人口5万人富里市誕生。
以上、富里の地名が古文書などに初めて記されたことについて、年表形式で記してみました。図書館の2階に「地名から探る富里の歴史」という題でパネルを展示してありますのでご覧ください。
参考文献
富里村史 通史編
1981年7月 富里村史編さん委員会
※広報とみさとに掲載されたものを再構成しています。
お問い合わせ
富里市役所教育部生涯学習課
電話: (中央公民館) 0476-92-1211 (社会教育班)0476-92-1211 (文化資源活用班) 0476-93-7641 (スポーツ振興班) 0476-92-1598 ファクス: (中央公民館/社会教育班/文化資源活用班) 0476-91-1020 (スポーツ振興班) 0476-93-9640
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます