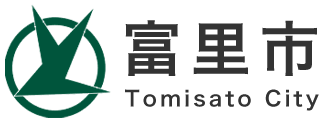地名に見る富里の歴史(旧石器時代からの営み)
- [更新日:]
- ID:2401
市制施行を記念して、「十三(とみ)の里」13の地名にまつわる地域の歴史を、市民の皆さんに13回にわたってご紹介していきます。第1回目の今回は、旧石器時代からのこの地方の営みを見ていきます。
富里を空から見ると、中央部から西側にかけて高崎川が流れ、その源は七栄地区、実の口地区、八街市文違にあり、その湧水は曲がりくねった谷津を通り中沢の小作地区で十文字に合流する特徴的な地形を示しています。
また、北東側には根木名川が流れ、その源は葉山と大堀にあり、根木名地区で合流するため、川の名前になったものと思われます。
富里には約3万年前頃の旧石器時代から人が住み付いたことが確認されています。この二つの河川周辺には原始・古代から人が住み、縄文時代から奈良・平安時代の遺跡が点在し、高崎川には新橋、中沢、立沢、高野、高松と、根木名川には日吉倉、久能、大和、根木名という集落が形成され現在に至っているものと考えられます。
中世頃から、下総台地は野馬が飼育されていたところで、千葉氏により野馬を管理する体制がとられ、江戸時代になり野馬の管理体制が強化されていきました。その野馬の管理で主要なものは、野馬土手の普請や牧場の整備でした。その野馬土手は、今でも国道296号線沿いで酒々井町に隣接するところや、409号線が交差する周辺や高野の工業団地の南側に捕込跡の土手が残っています。
明治維新の政変で江戸幕府が解体となり、武士などの救済のために内野牧・高野牧は開墾会社により明治3年に入植が開始され、開墾は入植の順番に美称が与えられ地名が付けられました。最初に入植したところが初富(鎌ヶ谷市)で、二和(船橋市)、三咲(船橋市)、豊四季(柏市)、五香(松戸市)、六実(松戸市)、七栄(富里市)、八街(八街市)、九美上(香取市)、十倉(富里市)、十余一(白井市)、十余二(柏市)、十余三(成田市)と開墾されました。
明治5年になり、内野牧が開墾されたところを七栄村として、また高野牧が開墾されたところを十倉村としました。
明治17年に七栄村外12か村連合戸町役場制が実施され、この十三の村(里)が富里の全域を締めることから、十三の里を美称して「富里」と称し、明治22年に十三の村は「富里村」として誕生しました。
次回からは、富里が村、町、市へと発展した十三の里の歴史について紹介します。

野馬土手

参考文献
富里村史 通史編
1981年7月 富里村史編さん委員会
※広報とみさとに掲載されたものを再構成しています。
お問い合わせ
富里市役所教育部生涯学習課
電話: (中央公民館) 0476-92-1211 (社会教育班)0476-92-1211 (文化資源活用班) 0476-93-7641 (スポーツ振興班) 0476-92-1598 ファクス: (中央公民館/社会教育班/文化資源活用班) 0476-91-1020 (スポーツ振興班) 0476-93-9640
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます