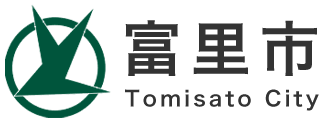令和6年度個人住民税(市民税・県民税)における定額減税のお知らせ
- [更新日:]
- ID:15317
1.制度の概要
令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税(市民税・県民税)において定額減税を実施することとなりました。
- 定額減税の概要は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
- 所得税の定額減税は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
2.対象者
- 令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の所得割の納税義務者で、合計所得金額が1,805万円以下(給与所得の場合、2,000万円以下)である方
※個人住民税(市民税・県民税)が非課税または、均等割のみ課税となる方は対象外
3.定額減税額(特別控除額)
定額減税額(特別控除額)は、次の1・2の合計額となります。
ただし、その合計額が個人住民税(市民税・県民税)の所得割額を超える場合は、所得割額が上限となります。
- 納税者本人:10,000円
- 控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき10,000円
※個人住民税(市民税・県民税)の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く)
例:控除対象配偶者と扶養親族2人の場合
本人(10,000円)+配偶者(10,000円)+扶養親族(10,000円×2人=20,000円)=40,000円
上記の例で個人住民税(市民税・県民税)所得割が30,000円の場合
所得割額が上限となるため、定額減税額は30,000円となります。なお、減税しきれなかった差額は、別途「調整給付」により、給付が行われます。
4.実施方法
個人住民税(市民税・県民税)の徴収方法によって実施方法が異なります。
給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分の徴収を行わず、定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの計11回に分割して徴収を行います。
※定額減税の対象とならない方については、通常どおり令和6年6月分から徴収開始となります。
定額減税額については、令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定または、変更通知書(納税義務者用)の摘要欄に記載されます。
普通徴収(納付書・口座振替等によりご自身で納付)の方
第1期分(令和6年6月分)から定額減税(特別控除)を行い、控除しきれない場合は第2期(令和6年8月分)以降で順次控除を行います。
定額減税額については、令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書の市民税・県民税・森林環境税課税明細2に記載されます。
公的年金などに係る所得に係る特別徴収(年金天引き)の方
令和6年度が年金天引き開始初年度の方
普通徴収(納付書や口座振替等によりご自身で納付)の第1期(令和6年6月分)で定額減税(特別控除)を行い、控除しきれない場合は第2期(令和6年8月分)以降で順次控除を行います。
定額減税額については、令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書の市民税・県民税・森林環境税課税明細2に記載されます。
年金天引きが前年度から継続となる方
年度後半の本徴収(令和6年10月分)で定額減税(特別控除)を行い、控除しきれない場合は12月分以降で順次控除を行います。
※年度前半の仮徴収(令和6年4月分、6月分、8月分)では定額減税を行いません。
定額減税額については、令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書の市民税・県民税・森林環境税課税明細2に記載されます。
5.留意点等
- 納税者からの申請は不要です。市において定額減税額を算出し、減税を行います。
- 定額減税の特別控除は、住宅ローン控除、ふるさと納税を含む寄附金控除等の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
- ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者※については、令和7年度課税分から定額減税を行うこととなります。
※個人住民税(市民税・県民税)の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く)
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます