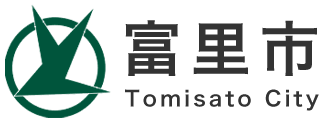年金からの特別徴収
- [更新日:]
- ID:9191
特別徴収とは
平成20年4月から、地方税法等の改正により、以下に該当される年金受給者の方(世帯)は、原則として世帯主の年金から天引きする「特別徴収」を実施しています。
普通徴収では、7月から翌年2月まで8回の納期でしたが、特別徴収では、その年度の国保税を4月から翌年2月までの「6回」支給される年金から天引きされることになります。
特別徴収の対象となる方(世帯)
次の1から3のすべての条件を満たす方は、年金から国民健康保険税を直接引き落とす「特別徴収」の対象となります。
世帯主が国民健康保険の加入者となっていること。
世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳であること。
特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと。
上記が一つでも該当しない場合は、特別徴収にはなりません。
なお、特別徴収の対象者となることが見込まれる方は、およそ2から3か月前に年金から徴収が開始されることについて、事前に通知を送付します。
世帯別構成による特別徴収事例
| 事例 | 世帯主 | 妻 | 子 | 徴収方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72歳(国保加入世帯主) | 68歳(国保加入) | ー | 特別徴収 |
| 2 | 72歳(国保加入世帯主) | 63歳(国保加入) | ー | 普通徴収 |
| 3 | 78歳「後期高齢者医療制度(擬制世帯主)」 | 68歳(国保加入) | ー | 普通徴収 |
| 4 | 72歳「社会保険加入(擬制世帯主)」 | 68歳(国保加入) | ー | 普通徴収 |
| 5 | 72歳(国保加入世帯主) | 68歳(国保加入) | 40歳(国保加入) | 普通徴収 |
6 | 72歳(国保加入世帯主) | 68歳(国保加入) | 40歳(社会保険加入) | 特別徴収 |
特別徴収の納付方法
(1)特別徴収の新規開始世帯(1年目)
| 納付方法 | 普通徴収 (納付書・口座振替) | 普通徴収 (納付書・口座振替) | 普通徴収 (納付書・口座振替) | 特別徴収 (年金天引き) | 特別徴収 (年金天引き) | 特別徴収 (年金天引き) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納付月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 納付税額 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
※端数金額を調整します。
- 7月・8月・9月は、普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。
- 10月・12月・2月は、特別徴収(年金からの天引き)による納付となります。
(2)特別徴収の継続世帯(2年目以降)
| 納付方法 | 特別徴収 (年金天引き) | 特別徴収 (年金天引き) | 特別徴収 (年金天引き) | 特別徴収 (年金天引き) | 特別徴収 (年金天引き) | 特別徴収 (年金天引き) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徴収種別 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 納付税額 | 前年度の2月に 特別徴収された金額 | 前年度の2月に 特別徴収された金額 | 前年度の2月に 特別徴収された金額 | 年税額残りの3分の1 | 年税額残りの3分の1 | 年税額残りの3分の1 |
※端数金額を調整します。
<仮徴収>
4月・6月・8月の特別徴収を仮徴収といいます。
4月・6月・8月は、前年度の2月の保険税と同額が、年金から天引きされます。
<本徴収>
10月・12月・2月の特別徴収を本徴収といいます。
10月・12月・2月は、年間保険税から4月・6月・8月に仮徴収した金額を引いた残りの金額を、3回に分けて年金から天引きされます。
特別徴収の対象となる年金
特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金および遺族年金で、受給額が年額18万円以上の年金です。
また、複数の年金を受給されている場合、下記年金保険者の優先順位により特別徴収される年金が決定されます。
複数の年金から重複して徴収されることはありません。
<年金保険者による優先>
- 厚生労働省(旧:社会保険庁)が支給する年金
- 国家公務員共済組合が支給する年金
- 日本私学振興・共済事業団が支給する年金
- 地方公務員共済組合(公立学校共済組合を含む)が支給する年金
特別徴収から普通徴収に切り替えとなる場合など
年度の途中で被保険者の異動等により保険税が変更すると、普通徴収への切替、または特別徴収と普通徴収が併用となることがあります。
【75歳に到達する年度】
- 年度途中に75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行いません。
【保険税が増額となった場合】
- 増額分については特別徴収できません。
- 特別徴収される保険税額のほか、増額分の税額については、普通徴収(納付書または口座振替)により納付して頂くことになります。
【保険税が減額となった場合】
- 原則的に、特別徴収を停止します。
- 異動の内容により特別徴収の停止が間に合わない場合がありますので予めご了承ください。なお、減少額によっては特別徴収を停止しない場合もあります。
特別徴収から「口座振替」への納付方法の変更手続き
特別徴収の対象となる方で、口座振替を希望される方は、国保年金課窓口に「国民健康保険税納付方法変更申出書」等を提出することにより、特別徴収ではなく口座振替による普通徴収で納付していただくことができます。
なお、4月に特別徴収が開始となる世帯(例年1月に対象者へ通知)、6月に特別徴収が開始となる世帯(例年3月に対象者へ通知)について、すでに口座登録を終えている方で、口座振替による普通徴収の継続を希望される方については特段のお申込みは必要ありません。口座振替から特別徴収へ変更を希望される方は国保年金課へ問い合わせてください。
※10月に特別徴収が開始となる世帯(例年7月に当初納税通知書と併せて通知)は、口座登録がある方であったとしても「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出をお願いしています。
※納付方法を口座振替に変更しても、保険税額は変わりません。
納付方法の変更は、「口座振替によることが条件」となります。
- 納付書による普通徴収には変更できません。
特別徴収または口座振替のみの選択となります。 - 世帯主以外の口座から引き落としを希望される場合であっても、納税通知書等の送付先は世帯主(納税義務者)となります。
特別徴収を停止し、口座振替による普通徴収が開始される時期は、「変更申出書」の提出後2か月以上かかる場合があります。
- 申出日の翌々月以降の最初の年金支給月から特別徴収を停止します。停止月以降の納期から口座振替での普通徴収に変更します。
口座振替による納付で滞納した場合
- 残高不足で口座から振り替えができなかった場合などは、特別徴収に切り替えることがあります。
納付方法変更申出書に必要なもの
以下の2点の書類を国保年金課窓口に提出してください。
国民健康保険税納付方法変更申出書
富里市預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
※すでに口座振替登録をお済みの場合は、(2)の提出を省略できる場合があります。
<窓口にご持参いただくもの>
- 金融機関届出印
- 預貯金通帳及びキャッシュカード
- 免許書等の身分証明書など
国民健康保険税納付方法変更申出書
様式は、国保年金課窓口に備えてありますが、こちらからダウンロードすることもできます。
国民健康保険税納付方法変更申出書
 国民健康保険税納付方法変更申出書(noufuhouhou-henkoumoushide.pdf サイズ:77.21KB)
国民健康保険税納付方法変更申出書(noufuhouhou-henkoumoushide.pdf サイズ:77.21KB)年金からの特別徴収の中止を希望する方は、国民健康保険税納付方法変更申出書を提出してください。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます