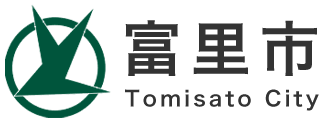オオキンケイギクの防除(拡散防止)にご協力ください
- [更新日:]
- ID:15214
オオキンケイギクは特定外来生物です
オオキンケイギクは、日本の生態系に重大な影響を及ぼすおそれのある植物として、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)による「特定外来生物」に指定され、栽培(植える、まく)、運搬、販売のほか、野外に放つことなどが禁止されています。
特定外来生物とは?
「特定外来生物」とは、外来生物法により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。
外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つことなどを原則禁止しています。
オオキンケイギクとは?
オオキンケイギクは5月から7月頃にかけて、鮮やかな黄色い花を咲かせる特定外来生物です。
市内の河川敷や道路脇などでよく見かけ、富里市内でも生息が確認されています。

和名:オオキンケイギク
科名:キク
学名:Coreopsis Lanceolata
原産地:北アメリカ
特徴:高さが30センチメートルから70センチメートル程度のキク科の多年生の植物。路傍、河川敷、線路際などに生息し、5月から7月頃に開花する。直径5センチメートルから7センチメートルの橙黄色でコスモスに似た花をつけます。
<出展:国立環境研究所ホームページ>
なぜ駆除が必要なの?
オオキンケイギクは、非常に生命力が強く、花も鮮やかできれいなため、かつては緑化用として道路の法面などに植えられたり、観賞用として苗が販売されたりしていました。
しかし、あまりの強靭さのため、定着すると在来野生植物の生育場所を奪ってしまいます。きれいだからといってそのままにしておくと、自然景観や日本国有の生態系を変えてしまう可能性があったことから、人の手でこれ以上広げないようにするため、環境省で、平成18年2月に「特定外来生物」に指定されました。
オオキンケイギクの駆除方法と注意点
オオキンケイギクは、栽培すること、生きたまま移動させることなどが禁止されています。
庭や畑など、ご自身の敷地内にオオキンケイギクが生えているのを見かけたら駆除しましょう。種子をつける前に駆除することが望まれます。
処理するときは、
- 根から引き抜いてください。
- 種がまき散らないように、ごみ袋に入れてください。
- 2日から3日程度、日当たりのいい場所で、枯死させてください。
- ごみの分別方法にしたがって処分してください。
また、特定外来生物についての見分け方は、
下記のリンク先にある、同定マニュアルを参照してください。
お問い合わせ
富里市役所経済環境部環境課
電話: (環境計画班)0476-93-4945、(環境対策衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529 ファクス: (環境計画班/環境対策衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます