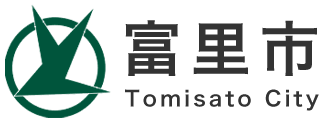令和3年度個人住民税(市民税・県民税)の主な改正のお知らせ
- [更新日:]
- ID:11587
令和3年度の個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点をお知らせします。令和2年1月1日から令和2年12月31日までに得た所得から適用されます。
1.給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
※給与所得控除の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】給与所得控除
2.公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円が、改正後の控除額から引き下げられます。
※公的年金等控除額の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】公的年金等の課税関係
3.基礎控除の改正
- 基礎控除の額が33万円から43万円に引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円超の場合は適用外となります。
| 合計所得金額 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 33万円 |
※特定の収入にのみ適用される控除(給与所得控除・公的年金等控除等)の金額が引き下げられ、どのような所得にも適用できる基礎控除の金額が引き上げられます。
4.各種所得控除の適用に係る合計所得金額要件等の改正
各種所得控除の適用に係る合計所得金額要件等が以下の表のとおり変更されます。
| 要件等 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |
| 家内労働者特例(必要経費の最低保障額) | 55万円 | 65万円 |
5.非課税基準等の改正
- 個人住民税(市民税・県民税)均等割の非課税基準が10万円引き上げられます。
- 個人住民税(市民税・県民税)所得割の非課税基準が10万円引き上げられます。
- 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件が125万円から135万円に引き上げられます。
6.寡婦(寡夫)控除等の見直し及びひとり親に対する個人住民税(市民税・県民税)の新たな税制措置の創設
寡婦(寡夫)控除等が見直され、婚姻歴の有無に関わらず、ひとり親に対して、以下の税制上の措置が設けられます。
- 前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税(市民税・県民税)を非課税とします。
- 前年の合計所得金額が500万円以下であるひとり親に対し、「ひとり親控除」30万円が適用されます。
注意事項
ひとり親が上記の非課税措置や所得控除の適用を受けるためには、各所得要件の他に、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない:住民票上の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」等の記載が無い
- 生計を一にする子を有する
寡婦に対する税制上の措置について
「寡婦」に対する税制上の措置については以下をご覧ください。
【夫と死別したか夫の生死が不明の場合】
以下のすべての要件を満たすと、非課税となります。
- 前年の合計所得金額が135万円以下である
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない:住民票上の続柄に「妻(未届)」等の記載が無い(本人が世帯主の場合は、世帯構成員に夫(未届)等の記載が無い)
以下のすべての要件を満たすと、寡婦控除26万円が適用となります。
- 前年の合計所得金額が500万円以下である
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない:住民票上の続柄に「妻(未届)」等の記載が無い(本人が世帯主の場合は、世帯構成員に夫(未届)等の記載が無い)
【夫と離別した場合】
以下のすべての要件を満たすと、非課税となります
- 前年の合計所得金額が135万円以下である
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない:住民票上の続柄に「妻(未届)」等の記載が無い(本人が世帯主の場合は、世帯構成員に夫(未届)等の記載が無い)
- 子以外の扶養親族を有する
以下のすべての要件を満たすと、寡婦控除26万円が適用となります。
- 前年の合計所得金額が500万円以下である
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいない:住民票上の続柄に「妻(未届)」等の記載が無い(本人が世帯主の場合は、世帯構成員に夫(未届)等の記載が無い)
- 子以外の扶養親族を有する
ひとり親控除・寡婦控除
1.前年の合計所得金額が500万円以下の「女性」に対するひとり親控除・寡婦控除の適用については、以下の表のとおりです。
| 配偶者関係 | 死別または夫が生死不明 | 離別 | 未婚 |
|---|---|---|---|
扶養親族:子有り | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 |
| 扶養親族:子以外有り | 寡婦控除26万円 | 寡婦控除26万円 | 適用無し |
| 扶養親族:無し | 寡婦控除26万円 | 適用無し | 適用無し |
2.前年の合計所得金額が500万円以下の「男性」に対するひとり親控除の適用については、以下の表のとおりです。
| 配偶者関係 | 死別または妻が生死不明 | 離別 | 未婚 |
|---|---|---|---|
| 扶養親族:子有り | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 |
| 扶養親族:子以外有り | 適用無し | 適用無し | 適用無し |
| 扶養親族:無し | 適用無し | 適用無し | 適用無し |
7.所得金額調整控除の創設
1.子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超え、以下のいずれかの要件に該当する場合は、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者である
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合は、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
※所得金額調整控除の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
8.調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除は適用外となります。
9.給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の改正
令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務対象となるかどうかの判定基準が引き下げられます。
【改正後の提出義務対象】前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上
※令和2年12月31日以前の提出分については、1,000枚以上
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます