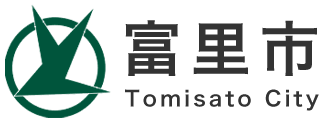とみさとの歴史(近現代)
- [更新日:]
- ID:2393
開拓の歴史
明治に入って、葛飾県・佐倉県・印旛県と3度にわたる所轄の変遷があったが、明治6年に木更津域とともに新しく設けられた千葉県域に含められることになった。
明治2年、東京府内の豪商は政府から依頼され、多くの窮民を集め開拓民としてこの地に送り込んだ。この時の開拓民は220戸を数え、七栄の原野の開墾に励み、一時はちょっとした繁華街ができるほど盛んであり、ここに七栄集落が成立した。翌明治3年には東京の開拓民と埼玉県あたりからの開拓民が十倉地区に集まり集落が成立した。現在の七栄や十倉という地名があるのは、開墾が七番目に行われた所が七栄で、十番目が十倉となっている。
しかし、開拓民の生活は苦しく、苛酷な労働に耐えきれず村を去るものが相次ぎ、明治8年の七栄地区の火災が追い討ちをかけ、開拓民の数は激減した。しかし、この後も開拓は進み両国地区に勧業寮本庁が設置され、ここにアメリカから牧羊家を招き、綿羊の飼育と洋式大農法を指導させることとし、下総牧羊場・香取種蓄場が開設された。
その結果、原野は整然たる耕地・牧場となり、羊群も散見できた。これらの事業は後の宮内省管轄「下総御料牧場」として発展する基となった。
明治22年には市制・町村制が施行され、日吉倉・久能・大和・根木名・七栄・新橋・中沢・新中沢・立沢・立沢新田・高野・高松・十倉が合併して「村」を形成することになり、その名を「十三の里」(里はむらの意味)ということから、「富里村」が誕生した。
明治後期から大正・昭和にかけての官有地の民間への払下げや戦後の農地開拓に伴い、開拓による入殖の受け入れで人口も増加し、ほぼ現在の規模になった。
開墾地は入植の順序と美称をくみ合わせて字(あざ)名としましたが、それが後に明治5年11月2日付をもって正式の村名に採用されました。それぞれの現在の行政区画は次のとおりです。
初富(鎌ヶ谷市)、二和(船橋市)、三咲(船橋市)、豊四季(柏市)、五香(松戸市)、六実(松戸市)、七栄(富里市)、八街(八街市)、九美上(香取市)、十倉(富里市)、十余一(白井市)、十余ニ(柏市)、十余三(成田市)
年表で振り返る富里の歴史
広報とみさと号外「市制20周年記念号」より
年表で振り返る富里の歴史
市制施行から現在まで
写真で振り返る富里市の20年
広報とみさと号外「市制20周年記念号」より
写真で振り返る富里市の20年
市制10年の歩み
「富里市制施行10周年記念誌」より
市制10年の歩み
お問い合わせ
富里市役所教育部生涯学習課
電話: (中央公民館) 0476-92-1211 (社会教育班)0476-92-1211 (文化資源活用班) 0476-93-7641 (スポーツ振興班) 0476-92-1598 ファクス: (中央公民館/社会教育班/文化資源活用班) 0476-91-1020 (スポーツ振興班) 0476-93-9640
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます